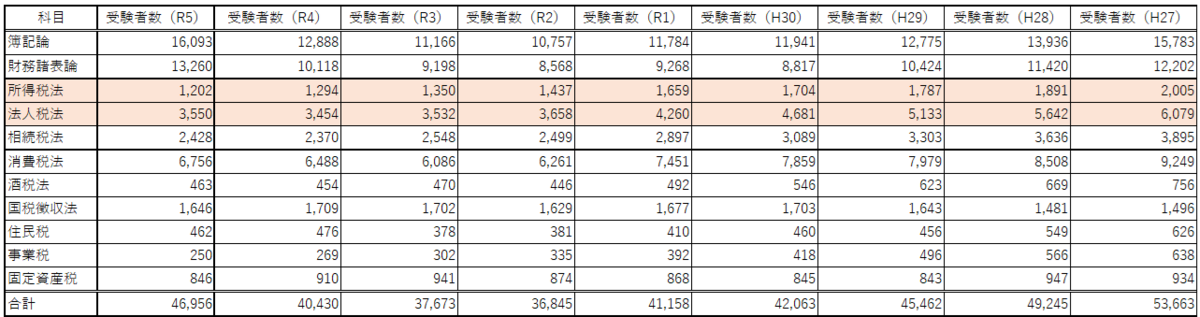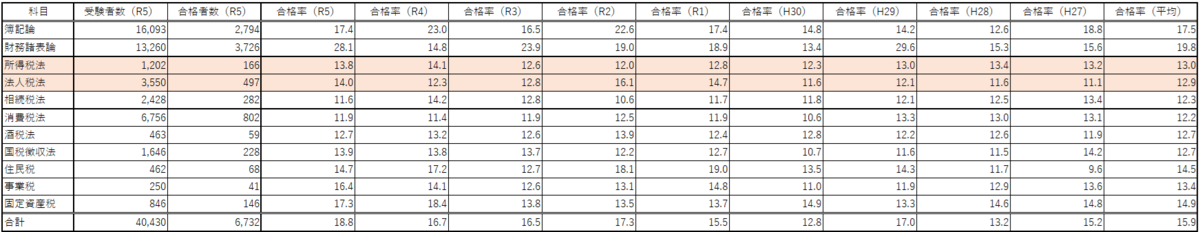こんにちは、T-アレックスです。
今回は英語学習の進捗についての記事になります。23年7月末にカランメソッドの受講を開始しました。Stage2は8月末に完了、Stage3は9月下旬に完了、Stage4は10月末に完了、Stage5は11月末に完了、Stage6は24年1月末に完了、Stage7は2月末に完了、Stage8は4月初めに完了、Stage9は5月末に完了、Stage10は8月上旬に完了しています。Stage11を完了したので記録を兼ねた記事を書きたいと思います。この記事にプロモーションは含まれていません。
1. 受講回数と時間
Stage11は70.5回で完了。その後Stage11の総復習(Full Book Revision)10回、合計80.5回(33時間32.5分)でした。受講期間は50日です。Stage11は136ページとStage10の120ページよりページ数が多いのですが、後述するようにStage11からはレッスン内容が変わっており、Stege10の81回より短い回数で完了しました。
基本的に平日は毎日1レッスン受講し、週末の土日は1日4レッスン受講しました。
QQEnglishの「よくある質問」にあるStage11完了までのレッスン数の目安は80回となっています。ほぼ目安のレッスン数で完了することができました。
2. Stage11からの変更点
Stage11になるとStage10までとはカリキュラムが少し変わります。
(1) 学習項目の追加
Daily Revision, New Work, Reading, Dictationがあるというのは変わりませんが、以下の項目が追加となっています。
① Word Pool : 15個程度の単語学習で、単語の意味と使い方を先生から聞いて学習するものでテキストに対応する質問文と回答文はありません。
② Phrasal Exercise:15題程度の文章の穴埋め形式の問題で単語や単語の変化を学ぶものです。Phrasal Exerciseの時はテキストを開いてレッスンを行います。
③ Emailやカバーレター、レポートの書き方:文章の冒頭や文末に何を記載すべきか、Introduction、Main Paragraph、Conclusitonに何を書くべきかなどを、他の例文と同じように質問と回答という形で学びます。
(2) Daily Revisionの短縮
もう一つ大きな変化は、Stage11からDaily Revisionで復習する文章の量が減ったことです。一つ一つの文章の長さはStage10と同じかそれよりも長いものもありますが、復習する文章の数が減りますのでDaily Revisionが早く終わります。これが、Stage11がStage10より早く完了した理由です。Stage10では1回あたり1.48ページ進みましたが、Stage11では1回あたり1.93ページ進みました。
(3) 単語・句動詞のレベルアップ
Stage11で出てくる単語・句動詞はStage10と比べてレベルアップしています。Stage10までは知らない単語・句動詞は2~3ページに1つぐらいでしたが。Stage11では1ページのうち半分ぐらいが、普段の仕事や会話で私は使わず、辞書で調べないと意味が分からない単語でした。調べてみると、実際の生活や会話で使われそうな単語や句動詞なのでマニアックな単語や句動詞が出て来ているわけではありません。
(4) 文法学習の終了
語句の説明(What is the difference between…)の文章は出てきますが、現在完了形はどんな時に使うかといった文法説明の文章は出てきません。
3. 受講スタイル
Stage2~10と特に受講スタイルは変えていません。単語のみ事前にテキストで確認しそれ以外の予習はしていません。リスニング力は上がっているので、先生の説明でNew Wordの意味は概ね理解できましたが、前述の通りNew Wordのレベルが上がっているので、事前に意味を調べておかないと意味を把握するのが厳しいものもありました。復習は1レッスンあたり30分でレッスン前に行っています。1レッスンあたり復習とレッスンで1時間かけています。長い文章が増えていますが、しっかりと復習をして文章を覚えることとDaily Revisionの量が減少したことで、Daily Revisionは10-12分で終わらすことができました。リーディングレッスンもリズも良くスピード感をもって読むことで、1レッスンで完了し次のレッスンに繰り越さないようにできました。Stage11は平均1レッスンで1.93ページ進みました。Daily Revisionの量が減少したので文章がさらに長くなってきましたがStage7の1.88ページ、Stage8の1.69ページ、Stage9の1.72、Stage10の1.48より進みが早くなり、Stage5、6の2.00ページぐらいの進度となりました。
4. カラン以外の英語学習
ELSA Speakでの発音練習を週2-3回の頻度で並行して行っています。未だにスコアは78-79あたりで伸び悩んでいます。単語練習では90点後半の点数は出るのですが、会話文になると70点代前半にとどまり、なかなか長い文章で発音の正確性を高めることが出来ていません。QQイングリッシュでは時々先生に発音を褒められますが、なかなか難しいです。実際に録音を聞くとまだまだというのが良く分かります。
Youtubeの英語学習動画を見てスクリプトに合わせたオーバーラッピングはやっています。語彙や表現の増加のための学習はしておらず、会社での会話やYoutubeの動画で使えそうな表現を真似することがある程度です。カランメソッドとは別に学習して語彙や表現の幅を広げる必要があると感じています。
5. 効果と感想
Stage5からは長い文章が増えており、New Workで先生の長い説明を聞いて覚えて、質問にフルセンテンスで解答するのは難しいですStage8からさらに長い文章が増えています。Stage11もStage8、9、10同様に長い文章も多いですが、Stage11でも復習をしっかりすればDaily Revisionではきちんと解答できます。
単語・句動詞の難易度はStage11から上がったと感じています。普段使わない単語・句動詞が頻繁に出てくるようになりました。文法の学習はStage10までで完了しているようで、前日の通り文法に関する文章は出てきませんでした。
新規の単語・句動詞はカランのレッスンだけでは、使いこなせるようにならないので、実際の会話で使えるようにするには自分で練習する必要があると感じました。
Stage6完了の記事で書いた通り、Stage6を完了したあたりからかなり効果を感じています。会議で同僚の発言は前より聞き取れるようになり、自分の発言もある程度スムーズに言えようになってきました。スピード感も向上し言葉を上手く繋げて話せるようになってきました。
Stage11を完了し、リスニングの能力が向上し、口も大分回るようになってきた感覚はさらに増してきました。まだ、言いたいことが言えずに言葉に詰まることもありますが、良くなってきたと思います。
会話で使用する基本的な表現であればStage4まで、常会話でよく使う表現であればStage6までで十分であり、Stage4やStage6までを繰り返しやった方が良いという意見もあります。私は、友人との会話、ニュース、会議などで英語を聞き続けるスタミナと反応スピードを上げるために、文法の理解ができているという前提で、どんどん先のStageに進んで長い文章を聞いたり言ったりする方が良いと思います。文章が長くなると大変ですが、負荷をかけただけの効果はあると思います。
最終ステージであるStage12に進みました。日本に一時帰国予定の12月中旬までにはStage12まで全て完了したいと思います。レッスンの目安はStage11、12ともに80回で、Stage11は1カ月半で完了したので、これまでのペースを保って学習を続ければ、12月中旬までに十分Stage12を完了できると思います。
今回はここまでとなります。参考になればうれしいです。